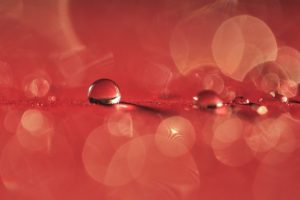永遠の夜の果て
3148文字。
本誌Z=219ラストの司千のためご注意。
状況は過酷ですが、甘めだと思います。
「俺たちは、長同士だからな」
心得たような顔でゼノが去り、元居室の上で二人きり。
月と星がまばゆいほど輝く空を眺め、南米復活の夜を思い出していると、千空がぽつりと言った。
それだけで言いたいことが手に取るように解った。
同じ言葉でたしなめられた時のことを、司はよく覚えている。
まだ付き合いはじめたばかりの頃だ。自分はもう長ではないと反論した司に、テメーは今も長だ、だからその自覚を持ち続けろ、と千空は告げた。
私情を廃し、欲を殺しても、皆の望む自分たちでいる必要がある、司にはそれが出来るし、そう出来る司だから好きなのだと。
――歯ァ食いしばって我慢すんだよ。
同じ時期、常に最適解を示してくれ、とも言われた。特に戦闘の分野では、常に専門家として分析し判断してほしい、自分はそれに必ず従うから、と。
実際そのようにしてきた。氷月を起こし、ドッグファイトを提案し、特殊部隊として潜入した。南米でコハクを追った時も、復活後残る判断をした時も、千空は否やを言わなかった。
常に最適解を望むのは千空であり、司はそれに応えてきた。今回もその結果だ。
誰に強制されたわけでもなく、司が自分で考え、確認し、決断し、千空に伝えた。そして千空は戦闘に関する司の判断に絶対に異議をとなえることはない。
そのことを、よく知っていた。知っていて進言した。
――自分の希望とは異なることを。
「君が残念だと思ってくれていることが、俺には嬉しい」
そう告げると、千空は静かにため息をついた。そんな仕草も、さびしげな横顔も、ずいぶん大人びたと感じる。
「そんな顔してるか」
「少しね」
「テメーの前でしか見せらんねえな」
千空は目を閉じると荒れた手を広げ、自らの顔を覆った。
そう、夜が明ければ自分たちは長の顔を取り戻すだろう。かれは何食わぬ顔で宇宙行きの人選を発表するだろう。そうして人々は、この夜に起きたドラマを知ることは決してないだろう。
そのことも、司は知っている。
「それでも、報われるよ」
「ほーん? テメーは俺よりずっと平気そうに見えるが?」
手から顔を上げ、じとりとこちらを見るすがたがいとおしかった。
「……平気だと思うかい?」
声量とともに感情をおさえた声で言う。視線がからむ。
星降るような夜空の下、気の遠くなるような長い時間、二人は見つめ合った。まるで彫像のように。逢えなかった長い時間を埋めるかのように。
司は自分の葛藤が、苦渋が、失意が、嫉妬が、伝わればいいとも、伝わってほしくないとも思った。
千空の前ではいつも冷静で完璧な自分でいたいと願うその一方で、剥き出しの自分を見てほしいという相反したきもちが湧きおこる。出逢った頃からそうだ。
「テメーの判断を信じてる。いつも」
つくろった声で、千空が言った。だがすぐに、「……だがな!」と力強く続けられた。
「他にもっとないのか! 久しぶりに逢って嬉しいとか、一緒に行けなくてさびしいとか!!」
怒ったような、拗ねたような声音に、じわりと熾火のような歓びが込み上げる。
かれがこんな風に駄々をこねる相手は今では他にいるのだろうか。離れていた期間、かれは誰かにこんな声を聞かせただろうか。
「千空が俺にそう駄々をこねてくれることが、うん、すごく嬉しいよ」
「すかしやがって。あいかわらず冷てえやつだ」
まだ言葉遊びの範疇だ。見極めながら、司は注意深く言葉を選ぶ。
「君は情緒全開でない俺の方がお好みかと思ったんだけど、違うかな」
「司テメー、どうした。ちょっと逢えないうちに、ずいぶんひねくれやがって」
きりりとした眉が吊り上がる。頃合いか、と判断して苦笑する。
「なかなか帰国の指示が出なかったものだから、多少拗ねてるかな」
「俺だって離れたくて離れてたわけじゃねえわ」
すなおでない恋人のその言葉は、「俺だって逢いたかった」と同義だろう。それくらいは解る。
「さびしかった?」
「今度はどうした、臆面もなく」
「俺はさびしかった。逢いたかった、いつも」
愕然とした様子の千空を見ないようにして、苦笑したかたちのままの口唇で本音を吐く。先に真情を吐露したらどうするのだろうという目論見があったのだが、案の定、茶化すことはできなかったようで、千空はうなりながら言葉を探した。
「……俺はテメーがいないことには慣れてるっちゃ慣れてるがな。今回は顔見に行くとかもできねえし、調子狂ったわ」
「俺がまだ冷凍庫にいるような気になってた?」
ささやくように言いながら、司は自分が凍っていた期間の千空に想いを馳せる。
そういえば一年半も眠っていたのだ。かれにとって自分がいないことは、それほど違和感があることではないのかもしれない。
「俺はね千空、君がいないと、ずっと太陽の昇らない永遠の夜の中にいるような心持ちになる」
南米で感じていたままのきもちを言葉にすると、千空はかすかに眉をひそめた。
「この世界に起きてから、君だけがずっと色あざやかなものだったからかな」
それを手に入れたくて手を伸ばし、激しく拒絶され、ならいっそと握りつぶしてしまったこともあった。
どうしてあんなことができたのだろうと今では思う。
「本当は、片時も離れていたくない。俺が君を守りたい。でも、俺が行くよりコハクが行くことで君の生存率が少しでも上がるのであれば、俺は行かない選択をする。それは最適解でもあるけど、私情でもあるんだ。――こんな判断をする俺はお嫌いかな?」
微笑に乗せた重い言葉を、千空は半ば目を伏せて聞いていた。月光に照らされた睫毛が、前髪が、銀色にけぶっている。司はそれを美しいと思った。
かれだけが色あざやかなもの。光輝くもの。
それに照らされ、初めて世界は色を取り戻すのだ。
「……テメーは、お優しいな」
やがて発せられた言葉は意外なものだった。
「冷たいんじゃなかったのかい」
「くっそ寒い台詞をいちいちくどくど言ってくるところは冷てえ気がするわ。口では人間、何とでも言えるからな」
「うん? つまり?」
「態度であらわしやがれ」
「――ずいぶん非合理的なことを言うね」
拳を口元に当て、この場でかれに触れていいものか考える。
ここは本拠地の最上階。下から見上げる者がなければ、誰の目にもつかないはずだ。
だが決断する一瞬の間も与えず、ひと回り小さいからだが体当たりするように飛びついてきた。脇の下から差し入れられた手がゆっくりと司の肩を抱きしめる。胸に顔を埋められる。
「るせえ、こっちのが合理的だわ」
もう待てないというようにあからさまな愛情表現をされ、司にもためらう理由はなくなった。
もう二度と離したくないのだというきもちを込めて相手の細い腰を抱きしめる。顔を下げ、頬の両側に髪が垂れるままにしてくちづけを落とす。
夜空に輝く月と星からも、二人の貌を隠すように。
「俺たちは長同士だからな」
司の腕にいだかれながら、千空は先ほどと同じことをひそやかにつぶやく。
司に言いきかせているようでもあり、自分に言い聞かせているようでもあった。
朝が来れば、二人は何ごともなかったかのように長の顔に戻る。別のドラマが始まり、同時に、再び別離までのカウントダウンが始まる。
だから日が昇り、陽光があまねく大地を照らすまで。月と星と科学の光が支配するこの夜の間だけは、恋人同士の顔をしていたい。
冷静な仮面を剥ぎ落として、他の誰も知らない、あるがままの自分たちでいたい。
「今だけは忘れて――千空」
互いが相手以外のことを考えられなくなるようにするため、暗闇の中でもまだまばゆいものに、司はゆっくりと触れていった。
了
2021年11月28日 twitterへ投稿