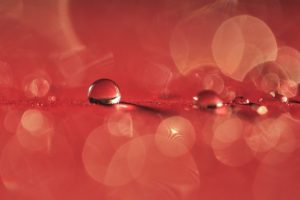Permission
2747文字。
人様への誕プレに書いたもの。時系列不明ですが、付き合ってる二人。
――また、あの目だ。
口唇を触れ合わせるだけの軽いキスの後、目を開いた千空はびくりとからだをふるわせた。
目の前の瞳の色に身が竦む。心臓が早鐘のように鳴り出す。ひゅっと喉が鳴る。
それに気づいたのか、手を離しながら司が困ったように笑った。
「千空。一度殺めておいて虫のいい話かもしれないが、どうか俺を怖がらないでくれ」
懇願するように言うこの美しい男が、誰に対しても以前よりとても丁寧な態度をとっていることは解っている。
見せる笑顔も、はりついた無理な笑みではなくなった。勿論天真爛漫を装ったりはしない。この男の現状に相応しい、どこか憂いを感じさせる柔和な笑みだ。
普段は無表情に近いが、威圧的にならないよう気をつけているのがよく解った。獅子王司は、そのように完璧に自分をコントロールできる人間なのだ。
それが、全部の仮面を剥がしたようにギラギラした表情を見せる時がある。今のように、以前と同じ獰猛な捕食者の目を見せる時がある。大抵は二人でいる時だ。
これは違う、違う意味だとは思うものの、それが何の違いなのか解らず、千空は声を失ってただ身を震わせることしかできない。
殺された時の恐怖と哀しみが蘇る。一度染みついてしまったそれは、どう合理的に、冷静に、この男はあの時とは違うのだと否定しようと、忘れられるものではない。
ああ、テメーにとって、俺はやっぱりいらない人間なんだなと。
俺がどんな人間でも、何を考えていても、テメーのことを好きでも、関係ないんだな、テメーは俺を殺せるんだな、と。
そんな絶望に、胸が黒く塗りつぶされていく。
自分という人間を、まるごと否定されたような感覚に陥る。
――やっぱ、ダメなのか。
あまりに衝撃で、感情の放出をおさえることができなかった。それは口から言葉で飛び出すのではなく、目からころりと零れ落ちた。
「な、泣かないで」
「うるせー、テメーが泣かせてんだろ」
慌てたように手をうろうろさせる男から静かに身を引く。
石神千空は泣かない。原始の世界に一人で生きていた時も、幾度か絶望の淵に立たされた時も泣かなかった。唯一の例外は、たった一度、親を亡くしたと思い知った時のみだ。あの時は一人になってから泣いた。
今、霊長類最強とキスした後、その瞳が、顔つきが、以前と同じものだったからといって泣くのはどうなのだろう。そう思うのだが、自分がこれまでしてきたこと全部、自分の気持ちを全部否定された気がして、虚しくて悔しくてたまらない。
「ほんとに、いつまでたってもテメーは思いどおりになんねーな」
千空はぐいと拳で涙を拭うと、泣く自分を前に、どうしていいのか解らずにいる不器用な男に笑いかけた。
「テメーが未来を見る顔、嫌いじゃねえ。あんな風じゃなくても、あれに近い顔で見てくれたらって思うのに、」
そこまで言うと、相手ははっとしたように手で口元を押さえた。
「すまない。俺は今、そんな酷い顔をしていた――?」
「あ゛ー。あんな怖え顔で見ることないだろ。また俺のこと殺してえのかと頭バグるわ」
「ごめん、ごめん千空」
そう言うなり、司はぐいと距離を縮め、有無を言わさずこちらを抱きしめてきた。この男にしては、思い切った、大胆な行動である。
「な、何すんだ」
「顔より言葉より、きっと触れた方が解ってもらえると思って」
恋人の言い訳、そして行動としては悪くない。というよりは、正解はあきらかにこれしかないと思う。本当なら、涙がこぼれたところでこうするのがベストだった気もする。
――それでもまだ、遅くはない。
そう感じて、千空は少しからだの力を抜く。直前に見た司の表情は、動揺していたが真摯で、純情そのもので、好感のもてるものだった。
別に殺したいわけじゃなんだな、と解ると、一気に安堵が押し寄せた。相手に体重を預け、その筋肉の厚さと体温を感じ、心音を聞く。
「心臓バクバクじゃねえか」
クククと笑うと、「うん、だから解るだろう」と返された。相手の胸板に顔を埋めたまま、千空は首を傾げた。
「何が?」
「さっき、俺が何故『怖い顔』をしていたか」
「あ゛ぁ? 解んねえわ」
苦笑する気配に顔を上げる。解るわけがないと言おうとして、あまりに深い、美しい微笑が目の前に現れ、言葉を失った。
「――君のことが欲しいからだよ」
千空をいつも戸惑わせ、寂しがらせる恋人は、思いがけないことを言った。
「それを我慢してるから、きっと怖い顔になってるんだよ」
「ま、待て、また頭がバグる」
「俺もバグりまくってるよ」
面白いほど困った、恥ずかしそうな司の顔は、見慣れなくて、可愛いといっていいほど人間的で、千空は思わずぽかんとして見惚れてしまう。
「そんな顔しないで。もっとキスしてしまいそうになる」
また怖い顔にならないよう、困ったように笑うのが解る。これは、明らかに無理している。
なるほど、と思った。
「すりゃいいだろ」
そう言いながら、千空は相手の首に腕を巻きつける。相手の顔がちゃんと見えるよう、思いきり首を上げる。
欲しいものも、したいことも普段言わない男が、自分を欲しいと思うのならば。何かしたいと思うのならば。それが、殺すなどという物騒なことでなければ。
何でもしてみたらいいと思った。
千空自身も、興味がないこともない。
「テメーに噛み殺されそうな顔見せられるよりはいいわ」
本当に、蛇に睨まれた蛙のようになるから。恐怖だけでなく、哀しみで心を塞がれるから。
そんな思いをするよりは、したいことをしてくれた方がきっと悪くない。
というより、唆る、予感がする。
霊長類最強の男は、嬉しそうに笑った。
「――千空。好きだよ、好き」
そう言って大切なもののように抱きしめられ、頬に何度もくちづけられると、ぶわっと顔が熱くなる。
同時に安心感が生まれて、ゆるゆると体から力が抜ける。
想いを滲ませた声が心地よい。ああこいつは、こんなに唆る声を出せるやつだったんだ、俺にこんな焦がれるような声をかけられるんだ、と解って嬉しくなる。
この声があれば、きっと、あの獰猛な目を見たとしても、動揺しないはずだと思った。
「君が俺を全然警戒せず、腕の中にいてくれるのが嬉しい」
頬に頬を摺り寄せながら司が言う。そうして、美しい目でこちらを見つめてきた。
「好きだ――もう二度と、君を傷つけたくない。なるべく怖い顔にならないようにするから、だから千空、」
千空は、その先を言わせなかった。自分から顔を傾け、かたちのいい口唇にくちづけることで、許可の意を伝えた。
了
2022年11月13日脱稿