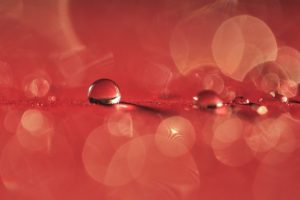フェリシア
5401文字。
「CAN YOU CELEBRATE?」の直後、瞼キスからの続きです。
何度も砂を吐いた…けど、ラストで立て直してます。
ふるえる瞼に敬虔にくちづけたこの瞬間を、きっと一生忘れない。
何もかもが報われた、と思った。
ぱさぱさと飢え乾いていた自分が、心から愛する人を得て、そのきもちを受け入れられたのだ。その記憶だけで、これからの人生を歩んでいける気がした。
おごそかな気分のまま、今度は秀でた額にくちづける。次に頬に。さらにもう片方の頬に。
くちづけたい場所にどんな意味があるかなど知らない。メンタリストに聞けば解るのかもしれないが、分析されるまでもない。ただ相手のどこもかしこもすべてがいとおしく、大切にしたいという気持ちがあふれて、からだが動いているだけだ。
目を閉じたまま俺のすきにさせてくれていた千空だったが、鼻の頭にくちづけると途端に笑い出した。
「くすぐってえ」
眠そうな声と赤い瞳にどきりとする。どちらもたっぷりと甘さを含んでいて、今まで聞いたことも見たこともないものだった。
うっとりと幸せになると同時に、重く頭をもたげ出すものがある。うすい口唇に視線が吸いつく。
――くちびるには、さすがに。さっき思いを告げたばかりで、それはさすがに。
そんな逡巡と葛藤を読みとったかのように、千空が俺のすぐ下で、ほっそり目を細めた。
「猫の子じゃあるまいし……じれってえわ」
「え?」
「くちには、しねえの?」
いっそあどけないといっていい表情で言われて、無意識に唾を嚥下する音が生々しくひびく。
「――いいの?」
呼吸と発声を何とか制御して、冷静さを装う。返答の代わりに、千空はぱちりと目を閉じた。
かれは自分のことに対してはいつでも潔い。男らしい。
こんな人が自分の想いを受け入れてくれたのだと感じて、ふるえるような感動が襲う。
大切にしよう。念じるようにそう思いながらゆっくりと身をかがめ、髪が垂れるのを片手で押さえて顔を近づける。
瞼へのくちづけに負けないほど丁寧に、引き結ばれた口唇に己のそれを重ね合わせる。
他のどの部分とも違うやわらかさに触れて、つきんとした痺れが脳にダイレクトに走り、背筋へ、全身へと広がっていく。
一切の欲を消した敬虔なくちづけのはずなのに、触れ合った部分から今まで感じたことのない熱が生じて、不思議な気分になった。
もっともっと貪りたいという本能を抑えつけ、無理やり身を起こす。至近距離で目が合う。相手のうるんだ瞳と目元の赤さにひゅっと喉が鳴りそうになるのを堪えて、もう一度額にくちづけた。
「……終わりか?」
ゆるゆると弛緩していくからだとかすれた声が、かれにも緊張と快感があったことを伝える。そしてその先、を嫌がっていないことも。
それだけで今は充分に満足だった。
「うん。今日はもう寝よう」
「俺が疲れてるって言ってたからか」
「それもあるけど」
もったいなくて、という言葉は飲み込む。
長い長い眠りから覚めたその日に特別なきもちが生まれ、それを受け入れられただけでも奇跡なのだ。もっとその僥倖に浸り、一歩ずつ関係を育んでいきたい。
だから、今夜この寝台で一緒に寝ることにすら、抵抗があった。
やはり自分は長椅子で、と振り返ったところで、寝台についていた腕のうち、首を曲げた側ではない方をぐいと引っ張られる。
「ちょっ、」
さすがにバランスが崩れ、とっさに千空を押しつぶさないようにしつつも、隣のスペースに転がるはめになった。
頬に当たる麻布のさらりとした感触。藁と皮と、動物の毛の匂い。そして、すぐそばにいる千空の匂い。
かれは寝台に広がった髪を押しやるようにして、顔だけ横向きになった俺と視線を合わせてくる。
「さっきから、どっか行こう、行こうとすんじゃねえ」
こちらを睨んで口唇を尖らせるさまがあまりにも可愛くて、半ばくらくらしながら敷布に顔面を埋める。
「――君は案外大胆だよね」
「あ゙? やっとテメー起こして、寝落ちじゃなくて頑張って寝ようとしてんだから、今夜くらい呼吸とか心音とか聞こえるとこにいてほしいわ」
「!」
瞠目する。
自分は何て愚かなのだろうと反省しながら、のろのろとからだを横向けにして、千空の頭が胸元にくるようにずり上がった。
今夜だけは、この存在は未来のようなものだ。そうイメージしていれば、何ということもない。
「……聞こえる?」
「おー、それにあったけえ」
満足気な声が聞こえて、ほっと溜息をつく。
ぺたぺたと胸板や腹筋を確かめるように触れてくるのが気になるが、昼間の触診と同じだと思えば、無視できなくもない。
やがて千空は一番鼓動がひびく場所を見つけたのか、そこに顔をぽすんと埋めた。
その仕草が幼くて、ドキドキするというよりも、雛鳥が懐に入ってきたような幸福感と庇護欲で胸がいっぱいになる。
抱きしめていいものか戸惑っていると、千空がぽつりと言った。
「冷たいテメーと寝るのはもうごめんだわ」
「まるで寝たことがあるみたいだね?」
冷凍睡眠前の話だろうか、と記憶をめぐらし、すぐに否定する。俺の体温が千空よりも低かったことなど一度もない。
「冷凍睡眠中の俺と添い寝を?」
胸に顔を埋めたまま、千空が大きく息をついた。
「聞くなよ」
「どんなシチュエーションなのか気になるよ。――何かつらいことでもあったのかい?」
「そうじゃねえ」
想定以上にむっとした声が返ってきてあわてる。無理やり未来だと思い込もうとして、感覚を混同してしまったのかもしれない。
千空という男は、つらいことがあったからといって、もの言わぬ人間にすがって寝るような真似はしない。そのことを、俺は知っている。
では――何故。
顔を覗きこむように首を曲げた俺の顎を手で押しやると、千空は顔を上げないまま、面倒くさそうに、簡潔に言った。
「台風ン時、とか」
愕然とした。
月に攻め込む、と言われた時より、もっとずっと衝撃だった。
「――ッ」
胸の中に、何かがしずかに降り積もってくる。
自覚したばかりの感情が暴走する。
何かがあふれ出るのを堪えるため、目を見開いて天井を見上げた。
神の存在を俺は信じない。それでも、かれの多幸と健康を、可能な限りこの世に生存し続けてくれることを、祈るような気持ちで願わずにはいられない。
――愛している。
その言葉は知っていたが、そんな気持ちを自分が抱けるとは思ってもみなかった。
「千空、」
声はうるんでいたが、不思議と相手にそれを聞かれるのは嫌ではなかった。
「どうしよう、君のことがすごく好きだ。――好きだ」
自分の胸に顔を埋めたかけがえのない存在を、その頭を、肩を、抱きしめる。抱きしめる。抱きしめる。
千空は腕の中で喉を鳴らして笑った。
「テメーそれ、カレシカノジョの感情じゃないんじゃねえ?」
「うん、もっと重いと思う」
「じゃなくて。俺に恩を感じてるだけじゃねえの?」
「なら、キスはしないだろう」
無粋なことを言いつのる口唇を塞ごうと、かつて手にかけた首に触れ、顔を上げさせる。
「お?」
驚いているというよりは好奇心の勝った表情を意外に思いながら、顔をかたむけてくちづけた。
今度は何度か角度を変え、口唇で相手のそれを食む。唾液が混ざり合い、ちゅ、ちゅ、とリップ音の鳴る、先ほどよりも官能的なキスになった。
ン、ン、と鼻に抜ける声と、時折びくつくからだが途方もなくいとしい。
銀の糸を引きながら顔を離すと、乱れた息の中、千空の目がほそめられていて不思議に思う。まばたきしていると荒れた手が伸びてきて、こめかみの辺りの髪をかき上げられた。
「まあ俺は、テメーに気軽にさわれて、生きてることがダイレクトに解んなら何でもいいわ」
「……それも、重いね」
胸がつまりそうになるのこらえ、目を逸らして軽く言おうとする。だが思いのほか感に堪えない声が出て苦笑すると、千空も肩をふるわせた。笑ったのだ。
顔を近づけ、視線をからめ、微笑み合う。
ばかみたいに幸福だと思った。
髪の中に差し入れていた千空の手がやわらかに動く。頭を撫でるような動きに、ごろごろと喉を鳴らしててのひらに頬を擦りつけたい気分になる。
やがて毛並みを撫でつけられるように後頭部にまわった手の動きに合わせて、かれの肩あたりに顔を埋めた。
血の匂いのする場所を注意深く避けて、かれがやっていたように収まりのいい場所を探し、その体温と鼓動を感じる。
かつて奪ったいのちが失われていないことを、こうやって確認するのは確かに悪くない。
一番近くにいて、触れてゆるされる他人。この位置を誰にも渡したくない、強くそう思う。
「千空。俺は、起こしてくれた相手なら誰でも好きになったわけじゃない」
「ん?」
こんなことを言うのも無粋かと思ったが、誤解があるなら今のうちに解いておきたかった。
「他でもない君だからだ。俺を警戒していた君、拒絶し続けた君、絶対に手に入ることなどないと思っていた君が、ことのほか俺を大事に思ってくれていたのが解って、感情が振り切れてしまった」
「ほーん」
顔を上げると、気の抜けた声とはうらはらの、思いがけなく優しい瞳がこちらに向けられていて、ぐっと胸が高鳴る。
「好きだ、千空。今は疑ってもかまわない。必ず信じさせてみせるよ。君を守り、支え、幸せにする」
千空はにっと笑うと身を起こし、俺のからだをよじ登るようにして再度おさまりのいい位置を探すと頭をもたせかけてきた。全身を預けてくる仕草がたまらず、壊さないようにそのからだをやわらかく抱きしめる。
そのまま深く息を吸い込むと、錆びた匂いの他に、確かに千空のものだと解る香りを感じて、途方もなく安心した。すきな人間の香りは、こんなにも人をリラックスさせるものだと初めて知った。
千空もまたふんふんと俺の体臭を嗅いでいる気配がして、臭くなければいいのに、と願う。狩りの後簡単に川でからだを洗ったが、まだ獣臭い可能性がある。
「……臭い?」
「いや。健康なテメーの匂いだ」
「健康でない俺の匂いも解ってるのかい」
「あ゙ぁ? 怪我してた時診察してたのは誰なんだよ」
思いがけない返事に驚いていると、尖った声を出される。
俺が千空の匂いを覚えているのは、ツリーハウスで隣に寝ていたということが大きい。氷月の槍に貫かれてからは、正直匂いどころではなかった。
「君は本当に、色んな俺のすがたを見てきたのに――俺を選んでくれるんだね」
感慨のあまり、心に浮かんだままが声に出て少し後悔する。これは俺の立場からすると、肯定されても軽くいなされても微妙な気分になる投げかけだった。
後悔が伝わったのか、千空はそれには答えず、からだに回された俺の腕を外させる。そうして頭の位置をずらし、曲げさせた腕の上に落ち着けた。
「俺を殺したこの腕が、これからは俺を守るんだって思ったら、唆るな」
腕に満足げにおさまりながらそんな風に応えてくれるかれがいとおしくて、額と頬にキスの雨を降らせる。
「ああ、俺が必ず君を守る。約束したように、思うように使ってくれて構わない。宇宙だろうが、危険があろうが、どこへでも行くし、何でもする」
「そうじゃねえよ」
千空は手を伸ばすと俺の前髪を引っ張り、噛んで含めるように言った。
「俺がテメーに期待すんのは、腕っぷしだけじゃねえ。テメーなら、俺が解んねえことも色々解んだろ。その時々で、テメーが最適と思うことを俺に教えやがれ。特にバトルはテメーが専門だ。戦闘のことは全部テメーに任せる」
「最適?」
「そうだ、これからは俺たちで最適解を導くんだよ。……唆るぜ、これは!」
嬉しそうな声が語るのは、愛の言葉ではない。このタイミングで、この態勢で、この雰囲気で言う言葉ではない。
――それなのに。
どうしてこんなに俺の胸にひびくのだろう、と思った。千空の言葉がうれしくてたまらない自分がいる。
出逢った時からずっと、俺はかれに、こういう言葉をかけられたかったのかもしれなかった。
「いいか、俺が欲しいのはテメーのぜんぶだ。お綺麗な顔も、ご立派なガタイも、出来のいいおつむも、面倒くせえところも、怖えところも、おやさしいところも、冷静に最適な判断できるところも、ぜんぶ。テメーから獣の匂いがしようが、上手におしゃべりできなかろうが今更どうでもいいわ。何もかも俺に見せて、よこしやがれ」
前髪を掴んでいた手はそのまま頬に触れ、かれの方に顔を向けさせられる。
赤いまっすぐな瞳を見て、ああ、そういうことか――と思う。すとんと腑に落ちるものがあった。
かれに肯定されるということは、そしてもしこの言葉を使うのが間違っていなければ――愛されるということは――こういうことなのだ。
これが本当に、「相手のすべてを求める」ということなのかもしれなかった。
「うん――俺は君のものだ」
この心臓も。命も。
重すぎると思うので、それは言わないけれど。
「だから千空、どうか俺を一番近くにいさせてほしい。いつも、どんな時も――」
もう一度、祈るように願う。
――最適解を。
時には情を殺して、自分を殺して、それを導ける人間になるから。
そうあろうとする自分でい続けるから。
いつも君の、一番近くにいたい。
嵐の日も、雪の日も。不安で眠れない夜も。
再び世界をあの光が包んだとしても。
何らかの事情で、たとえ一時期離れる期間があったとしても。
いつも君の――魂のそばに。
了
2021年12月03日 pixivへ投稿