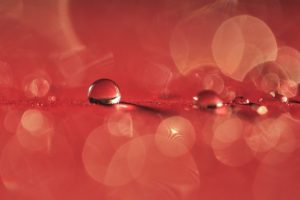月下の二人
2413文字。
南米復活直後エスケイプ司千。
せっかくのシチュなのに糖度上がらず…
「永遠の命を手に入れてしまった」
まばゆいほど降り注ぐ月光の中、この世ならぬ美貌の主が言う。
「ホワイマンのドクターストーンは、人類が触れてはならない科学の禁忌。禁断の果実だ――」
深刻な表情と声音。話を人類規模まで広げて世界を憂う、それがこの男の真骨頂なのだと改めて思い知らされる。
憂うといっても普段の物憂げな美女の眼差しではなく、その瞳は冷静でありながら剣呑な色に満ちている。かつて敵対していた頃を思わせる司の雰囲気に、茶化すこともできず、とりたてて反論することもなく、深刻じみた態度で付き合っている。
――だが。
(俺は多分、本当の意味では、コイツの懸念を解ってやれない)
(たった一人を救うために、冷凍睡眠、石化復活時の周辺修復力なんていう、確証のない奇跡に賭けた俺には)
あんな早い時期から、俺は禁忌の蓋を開いていた。そのことを、当の相手が解っていないことに少々驚いている。
冷凍睡眠の時点で既に生命倫理に触れていた。その自覚はあったから、「凍らせる」ではなく、あえて「殺す」という言葉を使ったのだ。完全に死んでいたのは俺も司も同じで、だから今回、絶命後まもなく石化した氷月がよみがえっても何の不思議もない。そうでなければ、俺も司も当時復活することは出来なかっただろう。
だか、どうやら司の認識では違っていたらしい。俺がかれを殺したことも、あるいはかれが俺を殺したことも、かれの中ではいつのまにか風化しているか、あるいは「死」は「仮死」に置き換えられているのかもしれなかった。
司の声を聞き、けざやかに光る川面を見ながら、俺は今までなるべく触れないよう、考えないようにしてきたことを、この復活の夜にあえて思い出していく。
誰にも言ったことはないが、俺が司に対して行ったあの蘇生処置は、今後他の誰にも使う予定のない、一回こっきりの大技だった。
滝やら何やら様々な条件の問題もある。解氷や凍傷の問題など、細かく気を遣うことも多い。いくら命の危機が迫っている仲間がいたとしても、常にできるようなことではない。
何より精神面の問題があった。あんな毎日歯の根が合わなくなるような恐怖を、ひと一人の生命を背負い、禁忌に手を触れている感覚を、毎回毎回自分が背負うのは絶対にごめんだった。
(コイツだったから)
つまり、かれを助けたい自分の問題だったから。何とか自分一人の胸の内で抱えることができた。
石化復活の仕組みも、その功罪も解っていないまま、起死回生の、その禁忌に賭けた。
どうしてあんなことができたのだろう、と今でも思う。
――あの時。
あんながむしゃらに、たった一人の命を繋ぎ止めようと、一本の糸にすがるようにして膨大な時間と労力をかけた。自分や他人の生命まで危険に晒した。この行為の延長線上に人類全員の救済があるのだと言い聞かせていたものの、そんな言い訳をしなければならないほど私情で動いていた自覚がある。
そこまでして、この男を失いたくなかった。
この命を終わらせてしまいたくなかった。生きていてほしかった。
あの時も、七年前も、今も、それは同じだ。
氷月だけでなく司も絶命していたとしても、それで蘇ったから何だというんだという気分が俺にはある。冷凍睡眠後の復活と同じだ。ただただ石化復活時の周辺修復力に感謝するだけだ。
だからそんな自分が、石化装置の是非を問えることなど何一つない。
(科学の世界では、百億年前から神は留守だ)
そんな風に言っても、目の前で深刻そうにご高説を垂れるこの男の胸には、ひびかないのかもしれない。
(たとえ禁忌の力でもいい。司、テメーが生き返ってよかった)
そう俺が言ってしまうことは、もしかしてコイツには解釈違いなのか。許されないことなのだろうか。俺たちはいつまで、七年越しの再会の場をこんな問答で埋めていなければならないのか。
俺より情緒ないんじゃないのかコイツ、大体起きてまず氷月を気にするとかどういうことだ、と半ば呆れ、半ば傷つきながら相手の顔を見つめる。月光に照らされた、稀代の彫刻家が苦心して作り上げた彫像のような、完璧な造形。
傷ひとつないこの顔、このからだに、今なら誰の目も気にすることなく触れることができるのに。よくできたメンタリストが、体を張ってわざわざこの時間をお膳立てしてくれているというのに。
(まあお互い、そういう風にはできちゃいねえか)
いつもいつも、死ぬか生きるかの修羅場続きで、恋人同士としてのふれあいも、どうしても生存本能からくる衝動に任せることが多かった。周囲を気にしてそれを押しとどめるとなると、ついこういったお堅い話になってしまうのかもしれない。
解るけどな、とため息をつき、無粋な恋人と目を合わせる。月光にきらめく瞳がようやくきちんと俺を認識する。
視線が絡まると、途端に焼けつくような衝動が全身を襲った。口から心臓が飛び出そうなほど動悸が激しくなる。
(なん、て目だ)
月光を映して赤みを帯びた瞳に宿るのは激情だった。自分を欲しがっているのがよく解る瞳だった。それを、鉄の仮面で覆い隠していた。
「石化装置の光は、死者をも蘇らせる。つまり、」
朗々とした声が、月と星に埋め尽くされた空に向かって響く。
復活したばかりであっても、司は冷静さを失うことはない。常に、そのようにあろうとする男だ。
感情を解き放つのは、本当に二人きりになった時だけだ。そして、かれはその獣じみた嗅覚や足の裏の感覚で、遠くの気配を正確に察知することができる。
「人類は皆この先、永遠に生き続ける――」
月面にいる敵に向け、美神の化身のような男は、壊れた石化装置を高く掲げて見せる。
クロムの声が響いたのはその直後だった。
俺たちが二人きりで再会を祝し合うまでには、まだ少し時間がかかりそうだった。
了
2021年10月26日 twitterへ投稿 司千1weekドロライ お題【月】【再会】