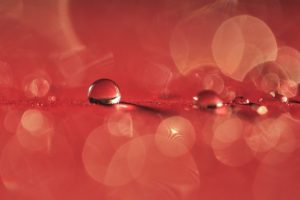この世界を照らすもの
6130文字。
「CAN YOU CELEBRATE?」の翌日の夜。まあまあ甘い。
Z=142の龍南シーンの直前だと思っていただければ。
昨日大樹と歩いた道を、今日は千空と歩いている。
船着き場からの帰り道。荷運びや保存食の調理、ロードマップの作製などで立ち働いていた面々はいつの間にか帰路についており、船の点検や修繕に勤しんでいた俺たちは取り残されたかたちになっていた。周囲が暗いことに気づいた俺が、まだ何かしようとする千空を引きずるようにして、ようやく船を後にしたのだ。
昨夜ここを歩いた時は腕の中で眠りこけていた千空は、今はとても元気そうだった。これまでのこと、これからのことを説明しながら隣を歩いている。
復活して二日目の夜だった。様々なものがまだまだ物めずらしく、俺は周囲を観察しながら興味深く千空の話を聞く。
「昨日も思ったんだけど、」
話が途切れたタイミングで、俺は広場のあちこちに設置された灯りを指さした。それらは海からの道にも点在していたが、広場に入ると急に数が増え、辺りはかなり明るくなる。
夜道に灯りがある、という光景に、俺はまだ慣れない。
「あの灯りは、俺にはすごく贅沢に感じてしまうな。今朝がた窓から見ていたけど、夜が明けるまでずっとついていた。君のことだから充分計算していると思うけど、いざという時のために節約しておかなくていいのかい?」
千空が意外そうな顔をこちらに向けた。そんな表情すらはっきり解るくらいに明るい。それがありがたいようにも、何だか惜しいようにも思える。
本当に月と星の明かりしかない、あやめ分かたぬ闇の中なら、もっと違う距離感、違う雰囲気で歩くことが出来ていただろうか。そんな埒もない、色惚けじみたことをつい考えてしまう。
「贅沢っちゃ贅沢だがな。女子供のこと考えりゃ、あった方がいいだろ。治安の良さと街灯の数は比例する。全員が気ごころしてれた村じゃ必要なかったが、村の人間と復活者が合流した今、少しでも揉め事の種は少ない方がいい」
「なるほどね」
俺にはない視点に驚いた。
先ほど俺がちらりと考えた埒もない妄想は、要は闇の特性から生まれたものなのだと悟る。明るいところ、人目があるところでは、ふつう人間は理性を捨てきれない。
千空は科学の力で、夜を、闇の持つ昏さを克服したのだ。
「仮にも長と呼ばれる立場だったのに――俺にはそういう視点はなかったな。うん、君はやっぱりすごいね」
「はっ、テメーの場合、自分の管理する場所で揉め事なんざ絶対起こんねえ、って自信があるんだろ。前提が違うわ」
千空は息を吐いて首を横に振った。
「揉め事がまったくないわけじゃなかったよ。俺が気をつけていようがどうしようが、暴力沙汰はともかく、人のきもちまではどうしようもできないし」
「あ゙ー、痴情がもつれる、ってやつか」
黙って頷く。
女性が杠一人だった時も、常に大樹をそばにつけていたにもかかわらず、危ない時があった。自分が選んだ人間たちである。無理矢理どうこうするような連中ではないにしろ、情が生まれることまで制御することは出来ない。俺だって現在、たまにきもちをうまくコントール出来ずにいるのだ。せいぜい杠に忠告し、見回りを増やして注意するしかなかった。
「女性が多くなれば多くなったで色々問題が起きて、俺の手には余りそうな時もあった。千空ならどうするかな、とよく思ったよ。生きていることを知ってからは、村ではどうなのかな、と」
「そんなことで思い出すなよ」
「そんなことでだけじゃないよ」
千空ならどうする、と、実は始終考えていた。かれという男に、俺はずっととらわれ続けていた。
そのことが伝わってしまったのか、沈黙が下りる。何となく気まずくて照れくさくて、俺はあわてて話を戻した。
「君はきっとうまくやっていたんだろうな。昨日、未来が褒めてたよ。『女の子のことも解ってる』って」
「解ってるわきゃねえ。女心とやらは一生解る気がしねー」
「うん、そうだろうなと思うのに」
げんなりした顔を見て苦笑する。千空は少し首を傾げると、
「あ゙ぁ、でも、あいつらが安全面や衛生面で何を気にするのかは少し解る」
と思いついたように言った。意外な回答に、少し驚く。
「安全面と――衛生面?」
「杠を見てきたからな。と言っても、解らねえことも多いけど。だからテメーから逃げてる間も、この世界で何が要るのか、何が気になるのか、あいつにヒアリングしてた」
そういうところが違うんだな、と痛感する。
俺に対しても、まず「欲しいものは?」と聞いてきたかれのことを思い出した。
「だから単に、女友達がいるかいないかじゃねえの。あとは、言いたいこと言う女が周りにいるかどうかとか」
「厳しいな。確かに俺には女友達はいない。言いたいことを言える女性は――多分杠だけだっただろうな」
旧世界の頃から、女性には遠巻きにされるか、媚びた態度で近づかれるかどちらかだった。杠の率直な感想や女性ならではの提案は、とても建設的で具体的でありがたかった。
「じゃあこれからは、年頃になった未来がどう思うのか、アイツにとってどうなのか、安全なのか、って考えればいいんじゃねえ?」
「ああ――そうだね」
もっともな意見に首肯する。確かにそうだ。俺はもう、精神面での「持たざる者」ではない。
「本当に、君はすごい」
昨日からくりかえしていることを再度口にすると、千空はケッと息を吐き出した。
「すごかねえわ。俺は腕力も体力もどっちかっつーと女寄りだからな。力のある奴より、ない奴の気持ちのが解るんだよ」
「女寄り」
「コハクとかニッキーとかは別にしてな。こんな世界で、力のない奴がある奴と対等でいようとすんのは大変なんだよ。だから頭使って必死に考える。何があった方がいいのか、何を知っておくべきなのか、どういう状況にならないようするべきか。男でも大変だけど、女どものが大変だと思うぜ。テメーにゃ解んねえかもしれねえが」
千空の言っている言葉は解りにくかったが、考えているうち、出逢った頃のことが次々と思い出された。
「銃もないこの世界じゃ……」と繰り返していたかれ、「3つって言わなかったか?」ととぼけたかれ、夜中ひそかにクロスボウを作っていたかれ。そしてついには、俺を出し抜いて火薬を作ろうとしたかれ。
過剰な警戒だと思っていた。その警戒と拒否の態度にずいぶん傷つけられた。
だがあれは、千空にとっては、生きのびるためには当然の行為だったのかもしれない。今になって腑に落ちる。
――テメーにとっては、強すぎることはどうしようもないことなのに。
冷凍睡眠前に聞いた、苦渋に満ちた声が思い出された。
「石神村の奴らも司帝国の奴らも、基本的には皆気のいい奴らだ。でもテメーがさっき言ったように、人と人の間のことは解んねえからな。恋愛脳が絡むとなおさら」
「うん――解るよ」
実際、俺がここにいた時も揉め事はあったのだ。
「皆を信じてないんじゃない、でも、百パーの信頼なんてなかなかない。知ってるだろ、俺は常に最悪の想定をしてんだ。だからテメーのことも最初警戒した」
「ああ――うん、そういうことか」
先ほど回想していたことも、聡いかれには解ってしまったのだろう、出逢った頃のことを持ち出される。
明かされたのは、考えていたより随分ましな真実だった。常に最悪を想定していた、だから俺に対して百パーセントの信頼はなかった、という、単にそれだけの話だ。
そして、常に最悪のことを想定するかれは、基本的に誰のことも百パーセントは信用しない。
「大樹のことは百パーセント信頼してたよね。杠のことも」
言わずもがなのことを言うと、千空はすなおに頷いた。
「あ゙ぁ、旧世界から付き合いのある二人だけだ。その後味方にした石神村の連中も、ゲンのことも、途中までは信じきれてなかった。テメーらが攻め込んできたら、見きられて生贄に差し出されても仕方ねえとずっと思ってた。――あることがあるまでは」
千空の話を、痛みを持って聞く。
かれはこれまで、いくつのそんな「もしもの話」を想定し、いくつの対応策を考えて、一人でそれを抱えてきたのだろう。その内いくつの読みが当たり、いくつが無駄な懸念となったのだろう。
そう考えると切なかった。俺もずっと生きづらさを感じてきたが、かれも随分損な性格をしていると思った。
「それが――百パーになったんだ?」
ささやくように言うと、苦笑まじりの答えが返ってきた。
「あ゙ー、アホほどお人好しな奴らで、ならざるを得なかったな。その後も色々あって、今じゃ周囲に限っちゃ百パーだらけだ。警戒しようにも、もうどうやんのか思い出せねえぐらい、なあなあになってる」
「あること」とは何か、かれらに何があったのか、知りたい、と思った。俺と敵対していた間のかれらのことを、何でも。
そしていつか、俺の過ごしていた日々のこともかれに聞いてほしいと願った。かれの存在を希求し、渇望していた、だが決してそれだけではない時代のことを。
「テメーにもそうだ、司」
ふいに顔を見上げられ、名前を呼ばれて心臓が跳ねる。世界中でこの相手にだけ、こんな反応が起きることを少し不思議に思う。
「俺はもう、テメーを殺すどころか警戒すらできねえ。だから百パー信用するしかない。こいつはもう俺を殺さない、蹂躙しない、そう勝手に信じてテメーと向き合ってる、今も」
赤い瞳が闇の中で電灯の光にきらめいている。
宝石のようなそれに、まっすぐひたむきに見つめられ、胸の中に満ちてあふれ出すものがある。
「――テメーは? 俺のことを信用できるか? テメーは俺に何パー預けられる」
「百パーだよ、千空」
間髪入れず答えた。
こちらを見る信頼のまなざし。俺を必要とする態度。俺が、ずっと欲しかったものだ。
「勿論百パーだ。君を信用し、信頼してる。守りたいし、大事にしたい。決して裏切らないし傷つけないと誓う」
「バッ、テメ、そこまで言わなくていいわ」
目を剥いた後、千空は視線を外して耳を掻く。照れた時の癖だと、今ではもう解っている。
「千空。俺は、君が百パーセント俺を信じてくれていることが、この上なく嬉しいんだ」
照れているところ申し訳ない気もしたが、まじめにこのきもちを伝えておきたいと思った。
ずっと、ライオンを倒した俺だから警戒したのだと思っていた。例えば科学を愛するクロムのような人間なら、すぐにかれの信頼を勝ち得ていたのだろうと。
だが恐らく、大樹と杠以外なら誰でも同じことだったのだ。今になって解る。
そして千空は、そのことを俺にずっと伝えたいと思ってくれていたのだろう。
「言葉にしてくれたのもありがたい。また警戒されたら、というのは、俺にとってかなり切実な問題だから」
「昨日のテメー、何かそんな感じだったな」
千空がちらりと俺を見て言う。恐らく、昨日の俺の態度を分析して、早めに伝えた方がいいと判断したのだろう。
「俺はオツキアイすんの初めてだからな。しばらく緊張したり、ビクつくことがないとは言い切れねえ。その度に誤解されて言い訳すんのは合理的じゃねえ」
「――!」
耳を掻きながら言う千空の言葉に唖然とする。
思わず立ち止まると、振り向いたかれの眉がわずかに上がった。
「あ゙? もしかして前提違ったか?」
「違わない。違わないよ」
思わず強い口調で言い募り、相手の両肩に手を置く。
逃さないという勢いで力を込めると、「は、怖え顔」と千空は破顔した。
「それに痛え」
「うん、ごめん。ちょっと、びっくりするくらい嬉しくて」
慌てて手を離し、片手はそのまま口許を覆う。これは照れくさい時の自分の癖のようだった。
この歳になるまで、そんな癖が自分にあることすら知らずにいた。
「あ゙ー、力の差を考えた上で、せいぜい大事に扱いやがれ」
独特の満足気な笑みを見せると、かれはそんな風に許可の言葉を吐いた。「勿論」と答えながら、くらくらするような幸福感と酩酊感に耐える。
同時に、もしかしたらこの一連の会話は、今後の俺に対する牽制でもあったのかもしれないと思った。
人のきもちだけはどうしようもないから。恋愛沙汰が絡むとなおさら。
ふつうなら制御できるはずの衝動が、闇の昏さや、肯定の言葉や、触れる肌の熱さで、たちまち制御不可能にならないとも限らないから。
それでも自分を百パーセント信じて、警戒することもできない人間に対して、扱い方を間違えるなよと――それは、あまりにも穿ちすぎだろうか?
「絶対、乱暴には扱わない。大事にする。だから千空――君に触れても?」
決意を込めて言うと、千空は気圧されたように、「お、おお」と頷き、先を歩き出した。少々警戒されているように感じる。
「でもすげえ恥ずいから、ちーっとずつな。それに、こんなところではダメだ。明るいから、窓からめちゃくちゃ見えんだよ。街灯つけたことを俺に後悔させんな」
明け方、窓の外を眺めていた俺はそのことをよく知っている。
「オーケー」
物わかりよく言った後、「部屋でなら?」と付け加える。先を行く千空の足が早まった。おそらく盛大に照れているのだろう、急な坂道を大股でずんずん歩いていく。
「あ゙ー、俺は出発まで忙しいし、あんまあそこ使う気はねえ。今日はメンタリストから頼まれてるからテメーを上まで送り届けるが、その後はラボに行くから」
背を向けたままひらひらと手を振られ、思いがけないことを言われて意気消沈する。では、同じ部屋に帰られることを嬉しいと思っていたのは、自分だけだったのか。
「まだ怪我が治っていないんだ。夜はよく休まないと」
落胆の色を隠さないまま強めにそう言うと、千空がちらりとこちらを振り返った。
「だからもう治ってるっつうの。司テメー、解ってんのか。あの部屋の上には龍水が住んでんだぞ。そこでする話をテメーに聞かせるっつって、ゲンが今画策してる。ようするに、何でも筒抜けだ」
「なら、俺もラボに行く」
「テメーなあ」
聞き分けのない子どもに言うような苦笑混じりの声に、少しだけ勇気づけられる。
「触れなくてもいいから、君と一緒にいたい。そばにいたい」
手を伸ばしかけ、言動の矛盾に少しためらう。本当に、感情と行動のコントロールができない。自分が自分でなくなったみたいだった。
千空は中途半端に伸びた俺の手を見て、自分の手を見て、あきらめたように息を吐いた。
「あ゙ーもう、クッソ恥ずいな」
そう言って、手を伸ばしてくれる。かれの方から触れてくれる。
――ああ、ゆるされている。
泣きたいようなきもちでそう思い、かさついた手を握った。
あまねく修羅が満ちるこの地上で、たった一人光を点そうとする者。
――それが、君なら。
俺は君とその科学を守る盾となり、矛となる。そう強く念じる。
そうして、君の思いつく「最悪の想定」を、一つでも実現させずにすむように。代わりに、今後はもう少し明るく甘い、「もしもの話」を思い描けるように。それを、実現できるように。
今はまだ、未知の敵に身構えることしかできない自分だけど。想い人のその手に触れることすら、ためらうような間柄だけど。
いつか、きっと。
了
2021年10月22日 twitterへ投稿 司千1weekドロライ お題【もしもの話】