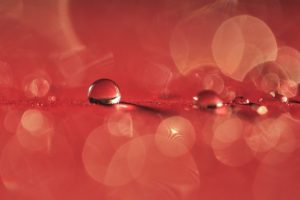闇に降る雨
6194文字。
コールドスリープ直前、雨の夜の司千、水分過多。
ツリーハウス時代に手に入れたかったもの。
滝の音とは異なる水音がする。
眠りと覚醒の狭間を彷徨っていた意識が、それに気づくと水面に浮かぶように浮上した。
雨だろうか、と考える。
いつも以上に重い湿気が立ち込めていて、四肢のだるさも増しているから、そうなのかもしれない。
薄く目を開く。灰色の雲が垂れ込めた空と水量の増した滝。ほの暗い灯りに照らされた洞窟の天井。岩壁。
壁際に転がっている男の気配。独特の髪型に覚えがありすぎて、司は一気に覚醒する。
「――千空」
溜め息のような声が漏れた。
夜の間、誰かが交代でついていてくれることになっていたが、千空がここに寝泊まりしたことはない。
彼は他にやるべきことが山積みで、同時にきちんと心身を休めることが大切だと、皆理解しているはずなのに。
「どうして誰も止めないんだ……」
「あー、明日まで大雨だからな」
思わず嘆息すると、場違いなまでに明朗な声が洞窟内に響き渡った。予想どおり、彼は眠ってはいなかった。
「こんなに降ってたら帰るのも面倒だし、このままここで寝て起きてすぐ作業入れる方が、俺には負担ねーんだわ。雨の日は他にできることも少ねえしな」
極めて合理的なことを言いながら、合理的な男が、ゆらゆらした影と共に近づいてくる。
情緒など欠落したように見せかけたがる彼の水分量は案外多いのだと、今ではよく知っている。
「それでも、君はこんな場所で休むべきじゃない」
「どうせ戻んのも似たような場所だし、似たような寝袋だわ。変わんねえよ」
近づいてくる千空の後方に目をやると、自分と同じような筵の上に、皮で出来た寝袋が投げ出されている。司は眉をひそめた。
彼が未だ戦時下のような生活をしているのは、恐らく自分が原因なのだろう。科学王国の長は毎日ここに顔を出し、冷凍装置か何かを作り、まったく休んでいる気配がない。
「俺の使っていた部屋は広いし静かだよ。寝台もある。使ってくれ」
「あー、落ち着いたらおありがたく使わせていただくわ。あんま寝心地いいと夕方まで寝そうで怖え」
そう言いながら千空はこちらの筵のすぐそばに腰を下ろす。手が伸ばされ、それが自分の長い前髪をそっと掻き上げるのを、司は不思議な気持ちで眺めた。
「――何?」
滝の音と雨音の他に、違う水音がまた加わる。額に置かれた布だか紙だかが冷たいものに換えられて、手桶の水を浸したのだと解った。
「今夜は俺がテメーの面倒みんだよ。大人しく看病されてろ。ご要望があれば何でも言いつけやがれ」
ククク、と笑いながら、楽しげな顔が近づいてくる。疲れてはいないようだが、それでも彼に看病させるのは気が引けた。
「特にないよ。大丈夫だから寝てくれ」
「何だよ、俺じゃ不満か? 下の世話だって何だって立派にしてやるわ」
「それは……すごく頼みにくいね。大樹だと気兼ねないけど」
思いがけないことを自信満々に言われ、ありのままの感想を言う。千空は僅かに目を剥いた。
「何でだよ。そこにどんな違いがあるっつーんだ。司テメー、俺よりデカブツの方がお気に入りか」
「違うよ」
何だか衝撃を受けているのが可笑しくて、黙っていようか一瞬迷った後、一応否定しておく。
「違う」
まだ何か言いたげな顔にもう一度強く否定すると、司は今では尿意はほぼないのだと付け加えた。
千空は眉をひそめると、細く長い息を吐く。
「そりゃあ――よくねえな」
初めて逢った時から自分のことを警戒ばかりしていた男、冷淡で薄情とさえ言えた男に、停戦直後から親しげに接され、生命を気遣われることに、司は未だ慣れずにいる。
未来のことを持ちかけられ、その復活に成功して、自分の中で千空の意味が大きく変わったのは当然だ。
だが、千空の中でどこからどんな風に自分の意味が変化して、これほど大事なもののように扱われるようになったのか、どうしても解らずにいた。
「雨で更に具合悪くなってねえか?」
こんな優しげな言葉も、視線も、ツリーハウスの数日間では得られなかった。
――もしもあの頃、こんな風に接してくれていたら。
違った結果になっていたのだろうか、と時折考える。
「湿気でだるいし、息もしにくいし、痛みも強いような気もするけど、うん、我慢できないほどじゃないよ」
「してほしいこと、ほんとにないのか。体拭くとか着替えるとか寝がえり打つとか。黙っててほしいなら黙る」
「特にないよ。黙っててほしいわけじゃなくて、君には休んでほしいかな」
「俺もテメーに寝てほしいわ」
微笑をかわす。
千空は壁際から筵と寝袋を引きずってくると、司のすぐそばにそれを設えた。灯りを消すと、洞窟内は真の闇になる。今夜の空には、月や星の光が一切ないからだ。
「よっし寝んぞ」
そう宣言した千空が、ゆっくり身を横たえたのを感じる。
闇の中、隣に彼の気配がある懐かしさに、一瞬、痛みもだるさも、すべての違和感が消し飛んだ。思わず手を伸ばし、これが熱に浮かされた脳が見せる、都合のいい幻覚や夢でないことを確かめようとする。
「何だよ、無暗に動くな」
寝袋に当たった手に動じることもなく、千空はそれを掴み、宥めるように撫でた。
羽のようなその感触に、「してほしいことは特にない」と答えたはずのかたくなな心が、もろもろと崩れ始める。
「――俺が眠るまで、どこにも行かないでくれないか」
「ああ」
「コールドスリープで眠る時も」
冷たいかさついた手が、柔らかく司の手を握る。
「ああ、最期までいてやるから、安心しろ」
何の警戒も緊張感もない、ただただいたわりと優しさのこもった千空の態度と声に、ゆるやかにほどけ、溶けてなくなるものがあった。
欲しいものはこれだった。あの頃も、今も。
声を発すると震えてしまいそうで、司は黙って荒れた手を握り返す。
――してほしいこと、ほんとにないのか。
先ほどの言葉を思い出し、鮮やかに蘇る記憶があった。
――司、テメーが欲しいものは?
雨。
雨の夜の記憶。
「俺が復活して二日目だったかな――うん。こんな雨の日があったね」
かすれた声で、ささやくように言う。
返事がなくても構わなかったが、千空は律儀に「ああ」と答えた。
司の復活初日。
ライオンを仕留めた後も狩りをして、大騒ぎしながら調理して食べてしまうと、皆疲れきってすぐ寝入ってしまった。
二日目は大雨になった。狩りに行くこともできず、湿気に満ちた狭いツリーハウスの中で、司は「詳しい説明」をゆっくり聞くことにした。
千空と大樹の関係、千空が目覚めてからの半年、大樹が合流してからの半年。これからの展望。彼らの話はすべて前向きで楽しかった。眩しいほどキラキラしていた。
「人類を、文明を復活させる」と聞いて、こんな子たちだからそんなことを思いつけるんだろうな、と、その時は微笑ましく思ったものだ。
千空の科学力も、復活液のこともよく解っていなかった。自分の復活は偶然にすぎないということも、大樹の想い人の次に復活するのは誰かということも、その後の順番や範囲についても。その日は何も考えずにすんだ。
ただ、それまでとは違う生活様式でどうやって生きていくのか、先に復活した友人同士の二人とどのような関係を築いていくのか――そういう現状に取り急ぎ対応することしか、すぐにはできなかったのだ。
だから、千空が寝る前に聞いてきた、
――司、テメーが欲しいものは?
という質問に対しても、深く考えることなく、「特にないよ」と答えた。先ほどと同じように。
だが、今なら解る。
あれは、単なる思いつきの質問ではない。
千空が司に何かしてやりたいと思って、この世界で不便を感じていたら解消してやりたいと思って、「欲しいものはないか?」と聞いたのだ。先ほどと同じように。
自分にそんな言葉をかけてくれる人間は今までいなかったから、司はそれを違う意味に受け取った。
「この原始のストーンワールドにいち早く復活して、男児たるものこれから何をしたい? 何を目指す?」
というような、漠然とした夢を聞かれたのだと思った。
そして、その晩は思いつかなかったものの、その答えを数日考え続け――遂には理想的世界の創造へと思い至る。
野ウサギのように警戒心が強い少年が見せた精一杯の好意に気づかず、その警戒を寂しく思い、野望をこじらせていった。
ただ、警戒を解きたいという意味でも、復活させてくれた感謝の意味でも、司は二人の役に立ちたいと純粋に願っていた。
千空と同じように、司もまた、彼らに何かしたいと願ったのだ。
自分の強みを活かし、積極的に狩りをした。司にとって、糧を獲得し、相手に腹一杯食べさせることは、もっとも解りやすい親愛の表現だった。
大樹の希望する肉を獲り、千空にも食べたいものは何か、何が必要なのか始終尋ねた。千空は大樹と同じでいいと言うばかりだったが、ようやく二日目の夜、自身の希望を口にした。
――今日みたいな雨の日に備えて、保存食になるものが欲しい。できれば魚な。
「……あの時は張り切ったよ。ライオンを倒そうがイノシシを捕ろうが鳥を捕ろうが、そこまで喜んでくれなかった君が、初めて俺に望みを言ってくれた」
「充分喜んでたじゃねえか」
夢見るように当時の心境を話すと、心外だというように千空が反論した。
「いや、喜ぶよりは断然警戒の方が酷かったよ。君にとって俺は、暴走したらどう止めるか常に考える必要のある、ただの危険人物でしかないのかと思った」
「そう見えたんなら……悪かった」
苦い声で謝られる。
謝罪してほしかったわけではないので、司は慌てて話題を変える。
「うん、だから、魚を獲って君が喜んでくれた時は嬉しかったな。ハイタッチしたのも初めてだった」
「ほーん。俺もテメーに何かしてやりたかったわ。でも『特にない』って言いやがるわ、必需品の石鹸作って見せたら、喜ぶどころか警戒しやがるわ……」
「そ、れは――悪かった。本当に俺は、解ってなかったんだ」
先ほどの自分と同じように恨みがましく言われて、司は苦笑とともに嘆息し、謝罪した。
「ああ? 何が」
「何もかもだよ」
あの日々の痛みを、焦燥を、不安を、苛立ちを、未だに覚えている。
それを千空に説明する気はない。理解してもらおうとも、何か言ってもらおうとも思わない。
ただ、当時の自分には、あれが限界だったのだと、今では解る。
お互いにやさしさを持ち寄って歩み寄ろうとしても。自分の側に、基盤となるものがなさすぎた。
相手の好意より、譲歩より、「警戒されている」「喜んでくれない」「自分は邪魔なのでは」「このまま科学が発展し、復活者が増えれば、俺は本当に用済みなのでは」と、悪い方向にばかり考え、それをこじらせてしまった。
千空の意図を正確に読み取ることができたとしても、「欲しいものは?」と聞かれたら、司は考えるよりも先に「特にない」と言うだろう。昔から、そういう子供だった。
それが旧世界で受けた自分の傷のせいなのか、本来の性格によるものなのか――考えたくはない。
だが今になって、あれは不幸なすれ違いだったのだということが、少しは解る。
始終警戒しながらも、千空は自分を追い出すわけでも大樹と場所を交換するわけでもなく、最後の日まで隣で眠ることを許してくれていた。そのことを、もっと素直に受け止めたらよかったと思う。
「俺も……解ってなかったな。自分の警戒がテメーにどう見えるのか。もっと違う対応があったんじゃないかって――殺された後で何度も考えたわ」
「後で?」
あの後でそんなことを考えていたというのが意外で、鸚鵡返しにする。千空は「後だ」と繰り返した後、一気に吐き出した。
「殺す直前に、テメーが言ったんじゃねえか。超非合理的な、あの場面に関係なさそうなことをよ。『友達になれたのかもしれない』って何だ? 友達だったらこうはならなかったのかと考えて気づいた。石化前の世界だったら、俺はテメーを危険人物だと見なさずにすんだ。俺たちが友達になれなかったのは、俺が最初からテメーを全身全霊で警戒してたからだ」
自嘲するような、絞り出されるような言葉の数々を、司は身を固くして聞いている。
こんな風に苦し気に、自分との思い出を語ってほしくはない。だが、敵対していた間、千空がこんな風に考えてくれていたのだと知ることができて、そのことは胸に染みいるほど嬉しかった。
「もしテメーが俺の次に復活した人間だったら、信頼するしかなかったはずだ。大樹の次だったから、俺らの都合で起こしたにも関わらず、テメーはすぐ警戒の対象になった。薄情だったと思う。テメーにとっては、強すぎることはどうしようもないことなのに」
苦い声をそれ以上聞きたくなくて、司は手を持ち上げると、千空が先ほど自分にしたように、額に垂れる前髪を掻き上げた。
その手に額をすりつけるようにして、千空が身じろぎする気配がする。
「テメーをあそこまで追い詰めたのは、俺なのかもしれねえ」
囁くように吐かれた言葉に、司は「それは違うよ」と窘めるように言った。
どんな原因があっても、自分で選び、自分で歩んだ道だ。そんな風に責任を感じられたくはない。
だが千空は、そのまま続けて、思いがけないことを言った。
「でも、そういう後悔があったから――いつか停戦できたら、テメーにもっとましな世界を見せてやりたい。そう思って――未来が復活して、うまくいったと思ったのに――こんな、」
そう言って自分の手を押しいただくように両手で掴み、身を丸めて喉を震わせてくれる相手が千空であることを、奇跡のように思う。
旧世界からのすべての苦労が報われたと思った。
しずかに感情の水位があふれて、相手を抱きしめたいと思いつつ、司は身動きすることもできなかった。
「千空、今俺は幸福だよ」
手から伝わる震えがおさまるのを待ち、ひそやかに今の気分を伝える。
「元気な未来を見ることができて、俺のことを警戒していない君とこうして話したり、触れたりすることができて、かつてないくらい幸福なんだ。本当に――ありがとう」
いらえはない。代わりのように、手がゆるゆると額から外され、薄い胸の上に置かれる。
「君がくれるものなら、生でも死でも受け入れる。目が覚めたあかつきには、好きなように俺を使ってくれていい。ただ――皆がどう思うかは解らないけどね」
「誰にも文句言わせねー体制作っとくわ」
そう言ってこちらに腕を押し戻し、クククと笑う様子はもういつもの千空で、司は安心すると共に少し惜しい気分になる。
この湿った空気の中、普段はドライを気取りたがる彼と、もう少し水分過多の話をしていたかった。それが無理なら――せめて触れていたかった。
そう思って投げた視線に気づいたのか、闇の中、白くふわふわしたものが近づいてくる。
「だから司、今度こそ、約束守れよ――?」
笑みを含んだ声でそう言いながら、千空は司の肩のあたりにそっと頭を擦り寄せてくる。
警戒心のかけらもないその仕草に胸がつまった。野生動物が思いがけず懐いてきたとしても、こんな感動は湧かないだろうと思う。
信頼と親愛の感触は豪奢で、到底手放しがたかった。
長い眠りから目覚めた後も、またこの感触が欲しい――と強く願った。
了
2021.06.13 twitterへ投稿 司千1weekドロライ お題「雨」